「余白の時間」が人生を濃くする。小学生のうちは週1回のクラブ活動で十分
さまざまなスポーツの競技団体関係者と毎月勉強会を開いていると、最善を尽くそうと思いつつも指導方法に悩んでいる監督やコーチが少なくないことを実感します。それゆえ彼らは、伝統的なやり方を踏襲して過度なトレーニングや、子どもを押さえつけた指導に偏ってしまいがちです。とりわけ日本のジュニアの未来を考えた時、ご自身の経験からどのような取り組みが有用でしょうか。

廣瀬氏(以下 敬称略):僕が大阪の吹田ラクビースクールに通い始めたのは5歳からですが、きっかけは両親に言われたからで、自分から頼み込んだわけではありません。だから、最初の1年は寒いし痛いしで、それほどラグビーを好きになれませんでした。それでもラッキーだったのは、そのスクールが「エンジョイラクビー」を標榜していたことですね。
勝敗にこだわるチームではなかったということですか?
廣瀬:そうですね。勝ち負けはコントロールできませんからね。そこにこだわらず、ラグビーのプレー自体を楽しむ、仲間を大切にする、そこを主軸にしてくれていたので、ラグビーを続けられたというのはありますね。
指導は厳しくなかった?
廣瀬:怒られることはありませんでしたね。スクールは週1回しかなかったので、他の曜日は好きなことに打ち込めました。あと、育成年代の指導という観点でいうと、高校での指導もその後の人生に大きな影響を与えていますね。
文武両道をうたう大阪府立北野高校ですよね。どんな指導だったのですか?
廣瀬:部の顧問は全国大会でも笛を吹いていた元レフェリーで、手取り足取り指導や指示を出すことはなかったですね。むしろ、プレー中に自分たちで考えろという主体性や自主性を重んじるスタイルで、いい意味で放任主義を貫かれていました。だから「花園常連校と比べて練習量が少ない分、頭を使ったプレーでカバーしよう」と、部員全員が同じ目標と課題をもって練習に取り組むようになっていましたね。
子どもの自発性や当事者意識を育むには時間がかかります。指導者にとっては忍耐のいる作業ですよね。
廣瀬:これからは、個人のアイデアや自分らしさが武器になる時代です。ほんの少しでいいので、選手を信じて裁量権を与えることは重要だと思いますね。「できる・できない」は才能やセンスによるところが大きいので、結果だけでなく「取り組む姿勢」や「態度」を評価する視点も忘れてほしくないかな。
大山さんはいかがですか?
大山氏(以下 敬称略):ジュニアに、ハードトレーニングは必要ないと思っています。私は小学2年生からバレーボールを始めましたが、小学6年生で身長が175センチだったこともあり、バレーボールのジャンプは身体への負担が大きく、中学に上がる頃には膝と腰のサポーターが手放せなくなっていました。高校ではその影響で足が痺れるように。結局、引退するまで腰の痛みを抱えたままプレーを続けるしかなく、完治することはありませんでした。
練習の頻度はどの程度だったんですか?
大山:私が通っていた小学校のバレーボールクラブでは週4日、夏休みや冬休みになると練習は毎日でした。これでも他の強豪チームと比べると練習量は少ないほうだったんですよ。
廣瀬さんと違い、バレーボール漬けですね。
大山:バシバシ叩かれて泣きながら練習していました。2時間「お説教」という日もありましたよ。だから、廣瀬さんの「ラグビースクールの練習は週1回」というのを聞いて、まさに理想だなと。
小学生のうちは週1回の練習で十分?
大山:それくらいでいいのかなと。小学生は「勝利」より「楽しむ」を優先していい時期だと思います。スポーツは人生を豊かにするためのツールのひとつですからね。スポーツだけに時間を奪われるのではなく、家族や友人と一緒に過ごす、勉強する、趣味に没頭する、そういう余白の時間を大人が作ってあげるのはとても大切なことだと思います。
廣瀬:それはあるかもしれませんね。日本では「全てを犠牲に……」みたいな姿勢が美徳として称えられる傾向がありますが、海外では「試合より大切な物はたくさんある」という考え方が当たり前です。だから、家族に何かあれば躊躇なく帰国する。大学を卒業して東芝ブレイブルーパスでプレーするようになって、海外の選手からそのことを学びましたが、最初は強烈なインパクトがありました。
才能が花開く前に選手が潰れてしまう……。過度なトレーニングと「勝ち」へのこだわりが生む悲劇
どの競技の指導者と話をしていても、「全国大会」という存在が勝利至上主義を生む要因のひとつという意見をよく聞きます。それについてはどう思われますか?
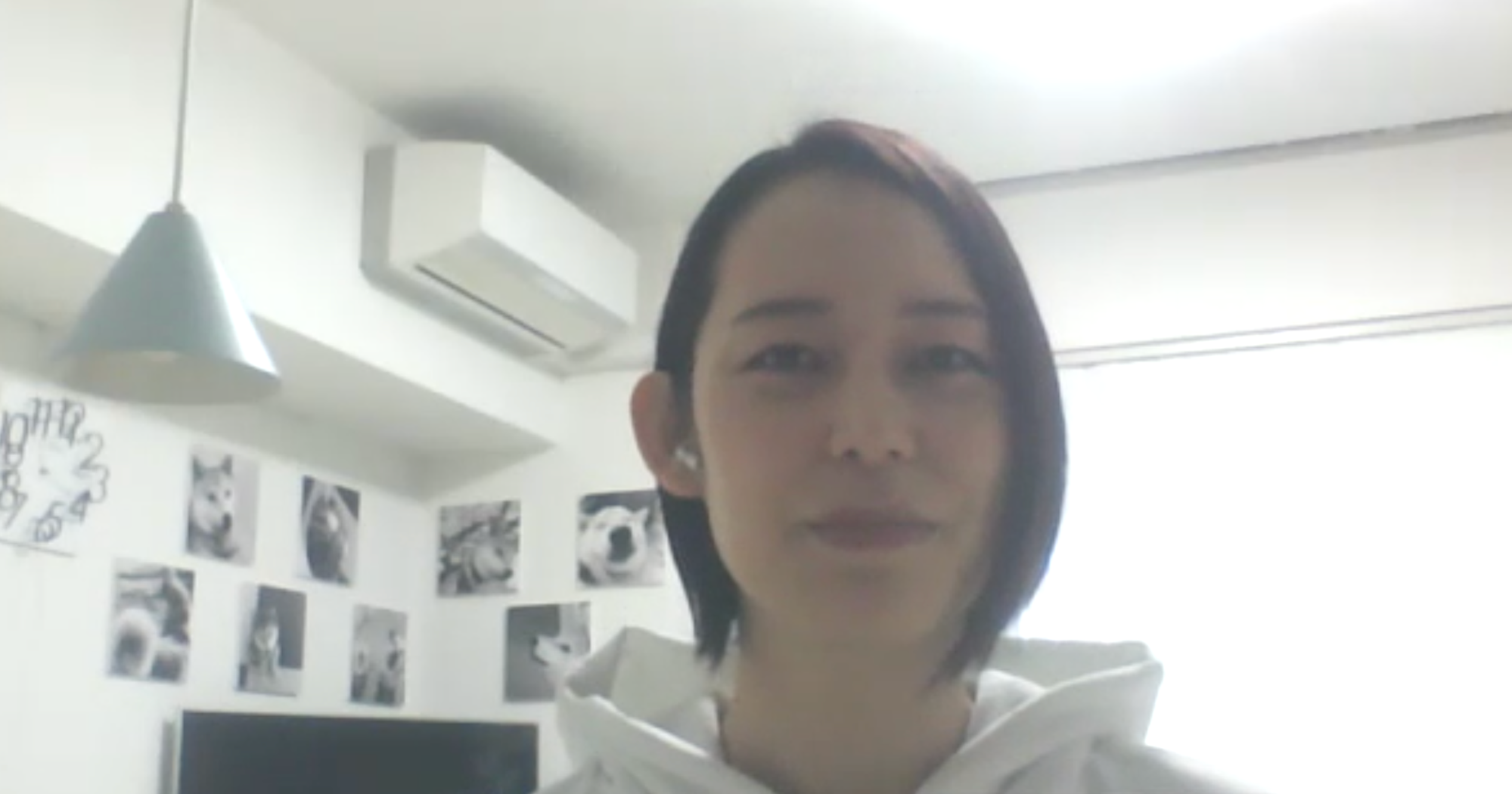
大山:ライバルとの競争によって成長していく。これはスポーツの素晴らしい側面ですが、そこに焦点が当たり過ぎてしまっている現状はいびつです。その結果、「勝利の追求」を子どもたちに押し付ける指導者は少なくありません。彼らの意識が変わらないのであれば、小・中学生の時期は地域のリーグ戦に留め、全国大会は高校から導入するというのも良策だと思います。
廣瀬:「勝つこと」に偏重し、身体ができあがっていないうちからトレーニングをし過ぎると、選手生命を短命にするリスクがあるので、特にジュニア期にはなくてもいいかもしれないですね。ただ、勝ち負けがあるからこそ打ち込めるという側面もあるので、逆に振り切り過ぎるのも良くない。難しいですが、ここの塩梅をどうするかでしょうね。
大山:知ってほしいのは、多くの才能豊かな選手が小さい頃の無理がたたって潰れてしまっているという現実が身近にあるということ。私の同期の荒木絵里香選手は、今年1月に発表された日本代表登録選手で主将に指名されています。彼女は高校から本格的にバレーボールを始めて、大きな怪我もなく今でも現役で活躍している。私自身はオリンピックという機会にも恵まれましたが、それでも彼女を見ていると、怪我のない身体で思いっきりスパイクを打ちたかったという思いに駆られてしまいます。小学生のうちは、スポーツ競技を好きになってもらうことを最優先、そういう思いがどうしても強くなってしまいますね。
自身はそのスポーツの経験がないのに、ジュニアの指導・育成に奮闘している指導者もいます。また、スポーツを通して成長してほしいと願う親御さんも多い。それが過度な期待を生んでしまうこともありますが、周りの大人はどのような姿勢でいるのがいいのでしょうか。
大山:スポーツは健康を害してまでやるものではありません。「勝ち」にこだわり過ぎて知らず知らずのうちに大人が子どもを追い詰めている。そういう一面があることをしっかり自覚して子どもの機微を捉える。そして、小学生の6年間、中学生の3年間という短いスパンではなく、スポーツを人生の一部として長い時間軸で捉えてほしいですね。
廣瀬:子どもが主役なのを忘れないことですね。親だからコーチだから偉いではなく、一人の人間としてしっかりと付き合っていくことが大切です。
スポーツ科学が発展してさまざまなトレーニング理論や健康法が手に入るようになっても、現場レベルでは前時代的な指導が続いてしまっている。コロナの影響でスポーツが難しい今、スポーツの在り方自体を考える機会になるかもしれませんね。
大山:スポーツは安心・安全の基盤があってこそ。一旦歩みを止めて、指導者も子どもたちもスポーツをやる意味や目的を考える期間にしてほしい。スポーツの在り方が変わる転換期になってほしいですね。
廣瀬:指導者にとって、今までの「当たり前」に疑問を持ついい機会だと思っています。ぜひ、ご自身がスポーツを心から楽しむ姿を子どもたちに見せてあげてほしいですね。コーチがスポーツを通して輝いている姿を見せることが、育成年代における最良の指導法のひとつであることは間違いありません。
聞き手/ユーフォリア社 代表 橋口 寛 文/谷口伸仁

