「What」の探究から「How」の探究へ
伊藤教授のキャリアの原点はスポーツバイオメカニクスなのですね。
スポーツ科学の世界では「What」を追求する研究が多いのです。アスリートを成長させるために、アスリートを変えるために、何をするべきか――という研究です。私もかつては主にそういう研究をしていましたが、そこで得られた知見をいかにアスリートに身につけさせるかという「How」の部分も同じくらい重要だと考えるようになっていったのです。
でも、そうした領域の研究はあまり進んでおらず、サイエンスと現場の間にギャップが生まれる一因となっていました。指導者を目指す学生らとの関わりの中でも、「How」を知りたいというニーズを強く感じることは多いです。
「アスリートセンタード・コーチング」は、そうした問題意識のもとで生まれたのですね。概念を提唱するに至った経緯を教えてください。
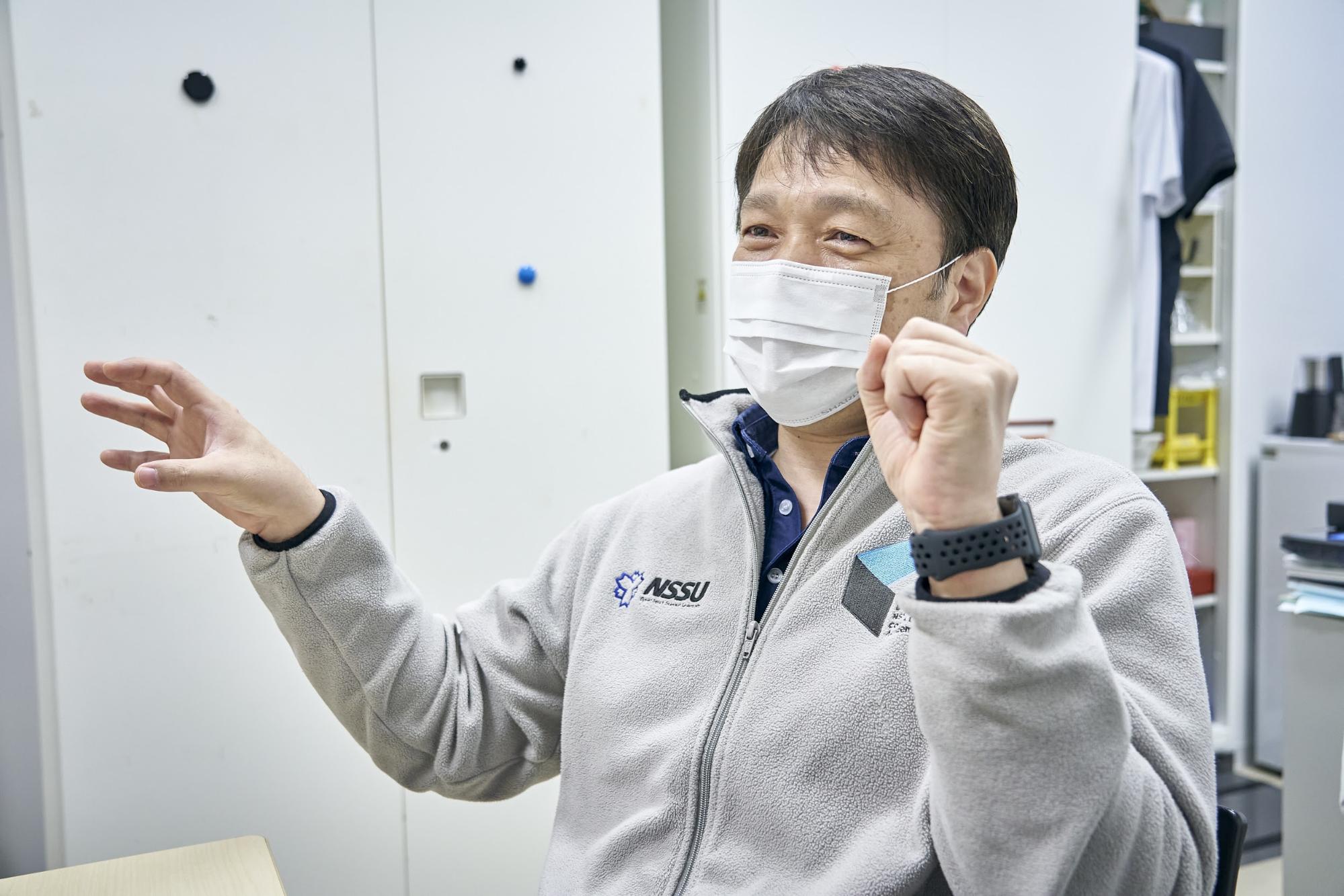
「アスリートセンタード・コーチング」とは、トレーニングは選手本位で行われることを基本としています。指導者は選手自らが学ぼうとする環境を整えることに注力し、成長を促そうというコーチングです。そうした指導が必要なのではないかという思いは、漠然とではありましたがかなり前から持っていました。
大学の授業などでも自分が主導して何かを教え込むのではなく、学生同士のディスカッションが活発になったときのほうが、学びが深まるという実感もありました。ただ、そういう授業にできず自分が教え込むかたちになってしまうことも多く、そうした場面でのもどかしさも、自分をコーチングの探究に向かわせた理由だったと思います。
「アスリートセンタード」に似た言葉として「アスリートファースト」という言葉がありますが、これに対する違和感もありました。アスリートがファーストなら、コーチはセカンドなのかと。そこに序列を設けるのは違うように思ったんです。海外では「アスリートファースト」という言葉はあまり聞かれないというのもありました。
そんな思いを抱きながら模索しているとき、リン・キッドマンという方たちが2005年に出版した『Athlete-Centred Coaching: Developing Inspired and Inspiring People』という書籍に出合いました。「スポーツにおいて、成績を伸ばす絶対的に正しい方法は誰も知らないのだ。にもかかわらず、指導者がアスリートに何かを教え込もうとするのは正しいのか?」といった問題意識から執筆された論考で、非常に感銘を受けました。それで、ニュージーランドに住むキッドマン氏を訪ね、行間に込めた思いや背景などを伺ったのです。そんな機会を経て、自分の中にぼんやりと像を描いていたコーチングの概念に「アスリートセンタード」という名前をつけさせてもらうことにしました。
公式に発信するようになったのは2011年4月からです。日本体育大学大学院体育科学研究科に体育実践学コースが新設され、コーチング学系(現・コーチング学専攻)ができたとき、プログラムで「アスリートセンタード・コーチング」として紹介したのです。
実際に世の中に周知していく段階に入ってからは、日本スポーツ協会とも議論しアスリートよりも対象範囲が広いプレーヤーという言葉を使い「プレーヤーズセンタード・コーチング」という名称も発信されてもいます。
アスリートセンタード・コーチングと放任は違う
アスリートセンタード・コーチングのポイントを教えてください。
アスリートセンタード・コーチングでは、選手の技術の習得には、選手に感情の動きが発生しているかが大きく影響しているという研究結果を重視しています。選手が自分でうまくなるためのイメージを描いて練習に取り組み、「できた!」という成功体験をする。それは誰かに言われて機械的な練習に取り組んだ結果の「できた!」よりもずっと深い技術の定着をもたらします。アスリートセンタード・コーチングでは、選手に主体的に練習に取り組んでもらい「できた!」や「やった!」を感じられる機会をいかにつくるかが、大きなテーマといえます。
それを阻害することがあるのが、指導者が抱く選手への期待です。特に指導者の頭の中にある正解をどれだけ再現してくれるか? という期待に基づく指導は、選手が主体的であろうとすることを阻みます。スポーツの指導における大きな問題と指摘されている体罰や暴言といったパワハラ指導も、指導者の期待と選手のパフォーマンスとの差から生まれるものです。
選手にうまくなってほしいと願い成長を期待すること自体は悪いことではありませんが、それが「指導者の頭の中にある正解」を選手が再現することへの期待になっていないかは、常に注意を払う必要があります。
私としては、指導者は「選手が自分の期待通りになるわけがない」くらいの思いで接するのがよいと思っています。選手が自分の頭で考えて下した決断は、全て受け入れる。そう決めればイライラすることも減るし、怒らずに済むのです。
指導者の意思ではなく、選手の意思ありきの指導ということですね。

そうなのですが、もしかするとアスリートセンタード・コーチングを放任のように思われる方もいるかもしれませんね。それは明確に違います。指導者は選手の選択を尊重するという前提は守りつつも、選手が自分にとってよりよい方法を見つけていくための働きかけは推奨しています。
指導者とは「化学反応の速度を変化させる触媒のような役割」で、自ら決定し成長していこうとする選手を見守り、その成長のスピードを速めるために関わっていく指導をイメージしてください。もうひとつ例えるならば、放牧され、各々自由に草を食べている羊の群れの周りを走り、それを外側から見守り、時に管理する羊飼いや牧羊犬のような存在というのも近いかもしれませんね。
選手本人の意思は尊重すべきですが、先に生きた人間として指導者がサポートできることはあります。選手が一人ではたどり着けないゾーンにいくための間接的なサポート――そのような立場からトレーニングをデザインするのが、アスリートセンタード・コーチングにおける指導者の役割だと考えていただければと。
選手の自主性を阻害しない範囲で、関わっていくためのコツはありますか。
コーチングにおける指導者の選手への関わり方は「Tell」(指示する・伝える)、「Sell」(提案する)、「Ask」(問いかける)、「Delegate」(委任する)の4つが基本です。「Teach」(教える)か? 「Coach」(助言する)か? という議論はよくされますが、私は指導においては、「教える」ことは必要だと考えています。ただ、「Teach」よりも少し弱い「Tell」くらいのニュアンスが妥当なのかもしれません。選手を見守る「Delegate」の段階に入る前に、指示や提案、問いかけといった方法でアプローチして、選手によりよい練習を選ばせる必要があります。
アスリート・アントラージュという言葉があり、選手をどのような人々で囲むか、その環境づくりの必要性はよく説かれます。そうした物理的な環境づくりから一歩踏み込み、選手がどれだけ学びを得られているかをしっかりと観察、評価して、その状況に合わせて適切な関わりを持つべきだと考えます。
そうした、どのように選手に関わるかという繊細な試行錯誤を繰り返すことで、コーチは成長していくものだと思います。アスリートを中心に据えなくてはいけない、質問をして考えを引き出さなくてはいけないというコーチ側の都合だけでコーチングをしている人もいると思います。それは選手に対するアスリートセンタードの押しつけという意味で、「コーチセンタード」の指導であるように私は思います。
即興的対応力をつけるために、指導者は「引き出し」を増やす
アスリートセンタード・コーチングでは、世代や性別、レベルに合わせた関わり方といった指針のようなものはあるのでしょうか?
どのような関わりが選手を主体的にして、よりよい成長につながるかはケースバイケースで、これだという答えはないと考えるべきです。それまでに受けてきた指導、親の関わり方、どんな経験をしてきたかなどで、適切な関わり方はまったく違ってきます。ハッパをかけることがプラスになる選手もいれば、マイナスになる選手もいたりするのが現実です。一概に「こうやればモチベートできる」という方法はほぼないのです。
だから結局、重要になるのは多くの経験を通じて培う即興力ということになります。選手に何か働きかけたときには、その後の反応を注視して、それが適切だったかほかにどんなオプションがあったかを振り返る。そうやってベターを探っていく。指導者が即興力を高めるには、そうした地道な努力を重ねていくことが欠かせません。
そこで私たちが有用であると考えているのが、コーチング・コミュニティ・オブ・プラクティス(CCoP)などとも呼ばれる指導者によるコミュニティをつくることです。指導者が自ら出合えるシチュエーションには限りがありますが、複数の指導者が経験を持ち寄り、語りあう場を設けることで、より多くの事例についての対応を思考する訓練ができます。
他者と一緒に指導について考え意見交換することで、ほかのチーム、ほかの指導者の考え方を知ることができますから、選手との関わり方の引き出しが増えていく。アウトオブボックス思考とでもいいましょうか。思考の外に触れてもらえる場をつくることは、コーチングのアップデートを図ってもらうための取り組みとして、私たちが最も力を入れてきたことと言えます。
選手の中に面白いという心情を芽生えさせる。感情がともなって印象に強く残る体験をさせる。コーチの役割の多くはそこにあるのだという考え方を、さらに広げていきたいと思っています。現在もハラスメントで苦しんでいる選手がいることを思えば、普及のペースは決して早いとはいえません。ですから、問題のある指導をルールで禁止することが必要であるという考えには同意しますが、真の意味でのコーチングのアップデートを実現するには、根幹の考え方を新しいものにしていく必要があると思っています。
過度な勝利至上主義が良くないという声も聞こえてきます。アスリートセンタード・コーチングでは、勝利を目標とすることに対しどう捉えているのでしょうか。
互いに勝利を求めて競うのがスポーツですから、勝利を目指していけないわけがありません。私も指導するチームや選手の勝利を、いつも願っています。そういうチームで指導に問題が生じているとすれば、その理由は勝利への執着よりも、指導する人の引き出しの少なさにあるように思います。大事なのはコーチングの質で、勝利にこだわったから勝てた、こだわらなかったら負けた、ということではない。選手本位のよい指導ができれば、自然とその先に勝利もついてくるはずです。
スポーツに根差す「文化」を変える困難
アスリートセンタード・コーチング普及の手応えはいかがでしょうか。

10年にわたりアスリートセンタード・コーチングの普及を図ってきましたが、関係者の意識が変わってきたことは強く感じています。一方で、長い時間をかけて築かれたスポーツ指導の文化を変えていくことの難しさを感じることもあります。以前、日本体育大学のある部で上下関係をなくすための取り組みをしたことがありました。それは順調に進み、部内の雰囲気は変わり、相乗効果で競技での成果も出ました。成功といってよい結果に終わったのです。
ただ、継続させることが難しい。上下関係の転換に中心となって取り組んだ世代が引退すると、徐々にかつてのような上下関係が再び生まれていったのです。「先輩たちとフラットに関わるのは気が引ける」という下級生たちの声が、関係をリセットさせた大きな理由だったようです。文化というのはやはり手強いです。長く引き継がれてきたものを変えるときには、変化をリードする人の継続的な関わりが必要。転換や改革が成功した後も、こまめに手をかけていく必要があるのだなと感じました。
今後取り組んでいきたいテーマはありますか。
コーチディベロッパーとして、指導者育成のノウハウをさらに磨いていくことが第一ですが、障がい者スポーツにおける指導にも関心を持っています。障がい者スポーツは、健常者のスポーツ以上に選手の個性に幅があることから、一人ひとりとしっかり向かい合った指導が必要です。ですので、これまでにどのようなコーチングがなされてきたのかを研究することは、アスリートセンタード・コーチングにも活用できる知見が得られるはずだと思うのです。
また、女性の指導者の育成にも取り組んでいきたいと思っています。アスリートセンタード・コーチングで欠かせない共感力、質問力といった要素に関しては女性のほうが得意とするという見解もあり、女性の指導者を増やすことはより多くの選手にとってのメリットとなる可能性があるからです。
スポーツの世界で、指導者や選手の親が変わってみせれば、世の中のさまざまな場面が変わっていくきっかけになると思っています。大きな転換が難しい教育分野などにも、いい影響を与えるのではないでしょうか。もちろん、私たちのやりかたはひとつの選択肢にすぎず、コーチングをよりよくするためのほかのアプローチもあるでしょう。押しつけることはありません。それでも、もし興味を持ってくださる方々がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒に取り組んでいきましょう。よろしくお願いします。
取材・文/秋山健一郎 撮影/堀 浩一郎

