障害ある子どもたちが当たり前にスポーツできる環境をつくる
パラリンピックに出場し、海外のチームでもプレーしてこられました。現在はどんなご活動をされていますか?

今は、企業のオリンピック・パラリンピック推進本部に籍を置いてフルタイムで働きながら、2014年に立ち上げたNPO法人D-SHiPS32(ディーシップスミニ)で、障害のある子どもが自由にスポーツできる環境を作るため、幅広い活動を行っています。今の子どもたちに、自分が感じてきた課題を残さないように、と考えているんです。
はじめは子どもたちに向けた取り組みをしていたのですが、そのためには親御さんの協力が必要だと分かり、親御さんたちのコミュニティを作りもしています。親御さんたちには、子どもにスポーツをさせる、心理的・時間的・経済的な余裕がないことが多いです。余裕がないのは、障害があることで困難な状況になってしまう社会課題があるから。今はそれを解決しようと取り組んでいます。
さまざまな課題がありますが、例えばパラスポーツだと、障害者が借りられる施設がとても少ないこと。数年前、私が国立の体育館を借りようとしたら、交渉は難航。ようやく許可が出ても、「床には全面シート、壁にはマットをつけてください」と言われまして。そんなこと、できませんよね。
最終的に、何とか体育館を借りることはできました。でも、私がもし小学生の子どもだとして「君は障害があって車椅子に乗っているから、この体育館は使えないんだよ」と言われたら、社会から否定された気持ちがして二度と外に出たくなくなると思います。この国は僕を受け入れてくれないんだ、と。子どもたちが自分の国に失望しない環境を作らなくてはいけないと感じて、変えようと取り組んでいます。
ほかには、道具が高価なこと。車椅子は一台30〜40万円以上します。しかし、子どもの成長は早いので小学1年生で買ったものが3年生には乗れなくなってしまう場合もあります。そこで、複数のサイズを用意しておいて、成長に合った車椅子を選べる「カリスポ」というサービスを始めました。今後は車椅子だけではなく、ホッケーをはじめとしてさまざまなパラスポーツ用品を揃えて貸し出せるよう、仕組みを作っているところです。
これまでパラスポーツは「障害者スポーツ」と言われてきたので、障害者にしかできないとか、健常者には関係ないものと思われていました。健常者と障害者のスポーツがきっちり分けられることが多いですが、アメリカでは地域のパラアイスホッケーチームに、健常者も入って一緒にプレーしています。日本にも同様のチームがあります。
どんな人でもできるのがパラスポーツなので、パラスポーツこそ「スポーツ」と呼ばれるべきで、健常者しかできないスポーツは「オリスポーツ」なのではないかと思うほどです。文化や慣習をひっくり返すことが、私の役目だと思っています。
現在のご活動を始められた経緯は?
2004年にホッケーをしに北米に行った時、障害のある子どもたちがいきいきとホッケーをしている姿を見たことに衝撃を受けたのがきっかけです。「いつか、こういう光景を日本でも作りたい」と感じて、社会人になって初めて自分で稼いだお金で、子どもたちのためのパラスポーツ体験会を開きました。
さらに、2012年にアメリカへホッケー留学をしたことも大きかったですね。チームメイトが、子どもたちへのスポーツの普及を推進している第一人者だったんです。色々な場所へ行き、色々な人に会わせてくれて、やりたいことが定まりました。
ある小児科医の先生ともお会いして、「障害を持った子の親御さんのサポートは十分ではないから、日本でもコミュニティを作ってくれるとうれしいな」と言われたんです。すぐには実現できませんでしたが、2014年にNPOを立ち上げたことで、先生からの宿題を実行する土台ができました。
自分のスペシャリティに気づき、生かす
選手時代に競技を通して学んだことをあげるとすると?

特にアメリカでアイスホッケーをしていた時に、学びが多かったと思っています。
一つは、スペシャリティ(強み)を生かすことの大切さ。日本は、ある程度なんでもできるジェネラリストを集めてチームを作りたがるのですが、アメリカはスペシャリストを集めてチームを作っているように感じました。ドリブルが得意な人、パスに特化した人、シュートがうまい人と、それぞれのスペシャルをつないでプレーしていく。自分の強み、弱みを選手が自分で理解しているし、選手同士が互いに認識し合っているんです。
それから、お互いを尊重するところ。どうしてもスポーツは失敗を責めてしまいがちですが、そうではなくポジティブな声の掛け合いで、お互いが向上していくことを学びました。
加えて、自分の意見をはっきりと言うことですね。アメリカでは、氷の上で意見を言い合って喧嘩になることもありますが、練習が終わったら切り替えて一緒にご飯を食べに行きます。オンとオフがはっきりしているところが面白いと思いましたし、私も意見が出せるようになりました。
こちらが発信しないと、私ができることも、何がやりたいかも伝わらないので、周りもサポートの仕方が分からないじゃないですか。自分の考えていること、やりたいと思っていることを恥ずかしがらずに伝えることで、それを実現するための仲間ができます。「仲間を集める力」が身につきましたね。
海外でのプレー経験は、現在の上原さんのお仕事にも影響を及ぼしていますか。
そうですね。例えばNPO法人を立ち上げた時、私はなんでも自分でやらなくてはと思い込み、ジェネラリストになろうとしていました。でも、自分が苦手なことに時間を費やすのは無駄だと気づいたんです。それからは、苦手なことはとにかく得意な人に任せるようにしています。
アイスホッケーでも、自分でゴリゴリ行こうとしすぎて、味方を使わないシーンはよくあるんです。でも、味方を頼った時こそ、点が取れるんですよね。ビジネスでも同じで、味方を頼ったりチームワークで進める方が、会社としても団体としても成長する。勇気を持ってボールを預けることは、非常に重要だと思っています。
また、子どもたちと接するときは、スペシャリティ(強み)を見つけてあげることを大事にしていますね。子どもたちは、親御さんや学校の先生くらいしか関わりがないので、何が強みで何が弱みか、まだまだ未開発の部分も多く、弱みが強みになる可能性もある。だから、一旦フラットに見て、まずは強みを見つけてあげる作業をします。

関わり方としては、探すというよりも「待つ」。ずっと待つんです、私。親御さんたちは子どもがやりづらそうなこと、困ったことがあると先回りして、すぐに手を出して助けてしまいます。手伝ってしまうと、子どもが本当にできるようになるのか、できないままなのか分かりません。だから、アイスホッケーの体験会でも子どもたちと親御さんは距離を置くようにしますし、親御さんと子どもたちを意識的に引き離すプロジェクトもやっています。「キッズチャレンジトリップ」といって、子どもたちだけを海外に連れていく企画です。
例えば、障害があって手に力が入りにくい子が飴をなめたいと思った時、いつもは親御さんが袋を開けてくれるんですよ。でも、旅の中では「どうぞ」と飴を袋ごと渡すんです。最初はなかなか開けられない。そこで「手だけでやってるからかもしれないね、ほかの方法があるんじゃない?」と考え方を伝えます。すると、歯を使うと開けられることに気がつくのです。たくさんの「できた」を届けることがテーマですね。
「できた」ことの中からスペシャリティが見つかるのですね。子どもたちへの接し方は、学ばれて?
自然とやっていたので、母の影響だと思います。私自身、母からいろいろなことを「できる」と教えてもらいました。母の基本は「できない」を言わない。私が小さい頃に自転車に乗りたいと言った時も、普通であれば「自転車は足で漕ぐものだから大祐は乗れないよ」と返すと思いますが、「ちょっと待ってね」と。タウンページを広げて全国の自転車屋さんに片っ端から電話し、手で漕げる自転車を見つけて「大祐、自転車だよ」と届けてくれました。
車椅子だから自転車に乗れないという先入観が母にあったら、タウンページを開くこともなかったはずです。初めからできないと考えないで、何かしらの可能性があるかもしれないと発想する。その考え方は僕も大切だと思います。
これは、パラスポーツも同じです。パラアスリートは、超人的身体能力を持ち、かつ工夫を極めています。例えば、上肢障害のあるアーチェリーの選手がいます。足が強いから、この強みを生かして選んだスポーツが、まさかのアーチェリーでした。足でつかみやすいよう道具を工夫して素晴らしい結果も残しています。
車椅子だからできない、目が見えないからできないという先入観も、パラアスリートを見ることで「なんで簡単に『できない』なんて言っていたんだろう」と思えるはず。腕がなくてもアーチェリーができるなら、足が動かなくてもできることがあるかもしれない。可能性を探し、発想の転換ができるようになるのがパラスポーツだと思っています。
指導者、補助具のメンテナンス人材、トレーナー、資金…… 足りないものはまだまだある。共感者とともに課題解決していく
最後に、これからの展望を教えてください。
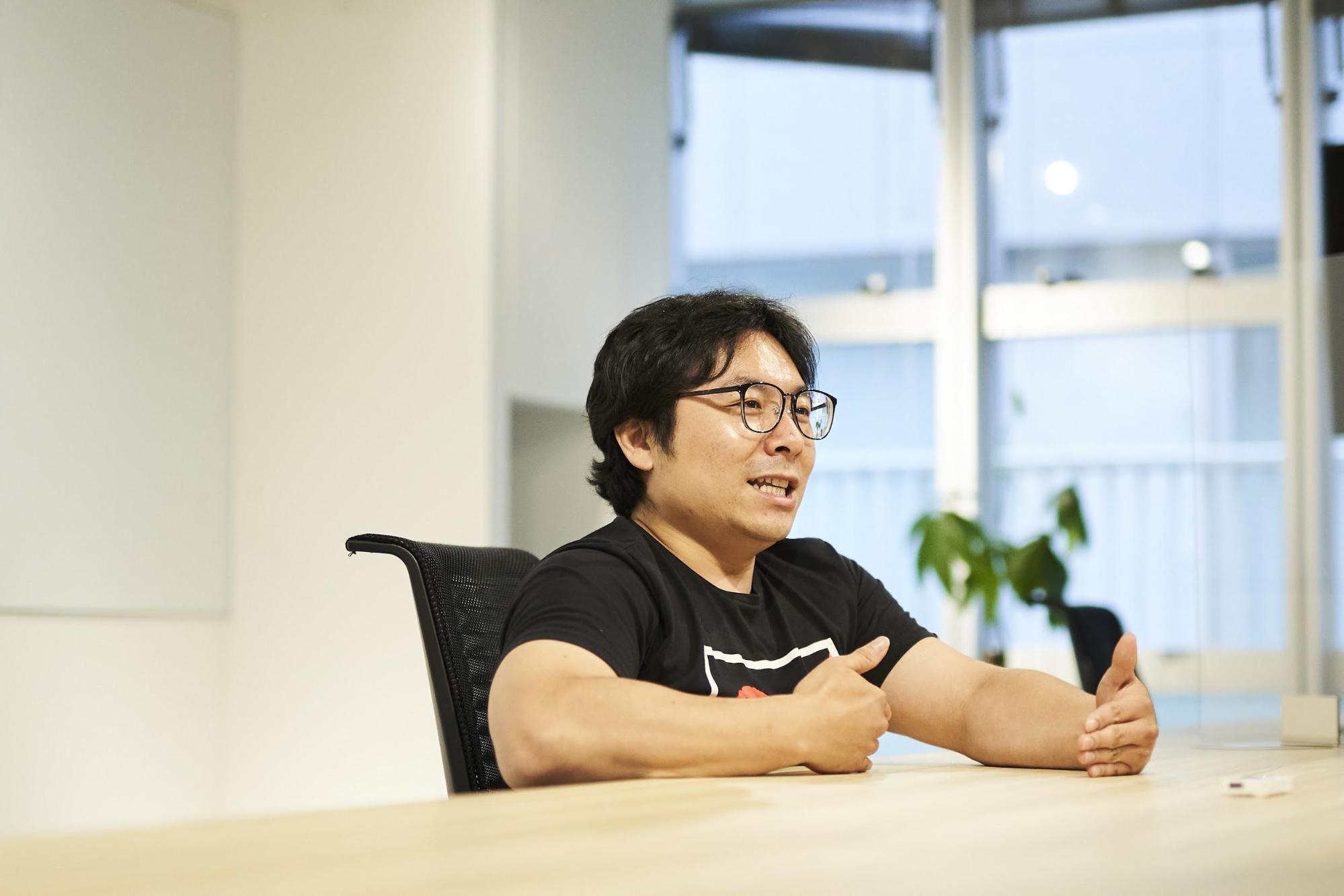
まず、自ら考え動ける選手の育て方を伝えていきたいです。今、パラアイスホッケー選手たちのコーチングにも取り組んでいます。私は身体が小さいので、それをカバーするためによく観察し、論理的に考えプレーに生かしてきました。どうすれば、強みを生かしてうまくなれるか、滑り方やハンドリング、パスの仕方を考えてきました。だから、子どもたちに教えるのも得意になりました。まず自分が頭の中で分析できていないと、選手には教えられないと感じています。
指導時にコーチが「こうしなさい!」と言うと、やれと言われたことをやるだけで選手は自分で考えません。指示通り動かそうとすればするほど、脳みそを使わない選手になってしまう。できなかったときに「なんでできないんだ?」と言うのではなく、「なんでそれをしたの?」と聞ける質問力、プレーを論理的に説明できる力、自分で考え答えを出すまで待てる力。指導者にはそのようなスキルが求められるのではないでしょうか。
そして、「カリスポ」を通して、スポーツと密接な関係にある道具、補助具がもっと手に取りやすい世界にしたい。私が2018年の平昌パラリンピックに行った時、車椅子やスレッジ(スケートの刃がついた専用のそり)をメンテナンスしてくれるメカニックが、日本のチームには帯同していなかったんです。他国のチームの友人に頼んで修理してもらったくらいです。
今カリスポでは、義肢装具士の育成カリキュラムがある学校と連携して、壊れた車椅子を学生に送り、メンテナンスして戻してもらう取り組みを始めました。将来のパラリンピック代表チームの専属のメカニックに、興味を持つ人が増えたらうれしいですね。他国のメカニックの中には、本業は自動車整備士の人もいたりしますから、必ずしもその道のスペシャリストでなくても関われる。そういうことを知ってもらいながら、活動を広げていきたいです。
自宅に眠っているスポーツ用品を貸し借りできるよう、「C to C」のサービスも始めました。道具を通してスポーツに関われる文化も作っていければと思っています。
あとは、パラスポーツに関わってくれるスポンサーに、価値を届けられる仕組みも作りたいですね。子育てサポート企業に「くるみんマーク」の認証があるように、パラスポーツ推進企業の認証マークを作ろうと動き始めました。ただ認証マークを作るだけではなく、取得後のメリットなどを含めた社会の仕組みづくりができたらいいですね。
子どもたちが夢を持ってスポーツをしたいと思っても、障害のある子どもは特にハードルが高く課題も多い。資金、指導者、道具、場所、トレーナーなどの専門職スタッフ、不足しているものだらけです。それらの課題解決を、私ひとりではできませんので、たくさん発信して共感者を集め、できる人に積極的に頼りながら取り組んでいきたい。当たり前のことを当たり前にできる世界にするために、ぜひ、多くの方に参画してもらいたいですね。
取材・文/粟村千愛、伊東真尚(ドットライフ) 撮影/小野瀬健二

